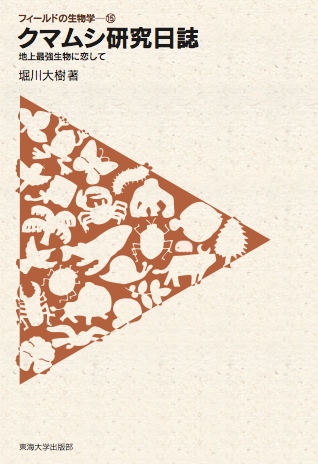レールを外れてクマムシ研究

クマムシは極限環境に耐える動物として知られる。私たちは今回、そのクマムシの中でも横綱級の耐性を誇るヨコヅナクマムシの高精度ゲノム配列を決定し、本生物の放射線耐性機構の一端を解明した。本論文はNature Communicationsに掲載された。
日本語のプレスリリース文はこちら。
ヒト培養細胞の放射線耐性を向上させる新規タンパク質をクマムシのゲノムから発見:東京大学
本研究の研究内容についてはプレスリリースも出ているので、ここでの解説は控えようと思う。その代わりに、ちょっと余談でも。
私がクマムシの研究を始めたのは2001年。まだ学部生の頃だった。たまたま配属された研究室の関教授がクマムシの研究をしていたことがあり、さらにOBの先輩から実際にクマムシを見せてくれた事が、クマムシ研究を始めるきっかけになった。
その後、大学院に進んでもクマムシの研究を続けようと決心していた。当時の指導教官の東教授はアリの生態学が専門だったが、「クマムシしかやりたくない」という私を受け入れて指導をしてくれた。余談だが、私は今、「アリしかやりたくない」という学生の指導をしている。何の因果だろうか。
さて、当時、頭の中にお花畑が咲いていた私は「クマムシの耐性についての研究はほとんど手付かずの状態で、自分でも何か面白い発見ができる。もしかしたら、第一人者にだってなれるかも」と思っていた。バカが考えそうなことだ。
当たり前だが、手付かずの研究分野には知見が蓄積されていないため、何から手をつけて良いのかわからない状態であった。クマムシがどんな餌を食べているのかも、ほとんど知られていないような状況だったのである。ちょっと賢い人間であれば、こんなリスクの高い研究など絶対に手を出さないだろう。
何とか生態学的な研究を行い修士課程を卒業したものの、クマムシ研究には限界を感じていた。実験室での飼育系も確立していない生物に、未来はない。そんなとき、幸運にも慶應義塾大学の鈴木忠さんが肉食性クマムシのオニクマムシの飼育系を確立した。この飼育システムを使えば、クマムシ研究は一気に進む。光が見えた気がした。
だが、いつも現実は甘くない。小さなクマムシを分析するには、多数の個体を集める必要がある。オニクマムシはなかなか増えず、ときには1日に16時間ほども世話をした事もあった。もはや、飼育ではなく介護だ。これでは、ゲノム解析にしろ、放射線耐性メカニズムの解析にしろ、実際にやり遂げるのはかなり難しい。
そしてオニクマムシに見切りをつけることに。新しく飼育ができる種類のクマムシを探しはじめたのである。博士課程2年のときだ。もちろん、飼育できるようなクマムシが見つかる保証は、どこにもない。博士号を取れず、ドロップアウトするリスクも覚悟の上での判断だった。
そして幸運な事に、博士課程2年の秋に、1種類のクマムシがクロレラを食べて繁殖することを発見。修士課程のころに、札幌市内で見つけた褐色のクマムシだった。

寒天培地の上でクマムシがどんどん増えていくさまを目にしていたこの頃が、これまでの研究人生の中でもっとも興奮した時期だった。
実験を重ね、この褐色のクマムシは他の種類のクマムシと比べてもだいぶ高い耐性をもつことがわかった。そこで、ヨコヅナクマムシという和名を与えてやった(学名はRamazzottius varieornatus)。単為生殖で増えるこのクマムシを1匹から増やし、標準系統も作り、これにはYOKOZUNA-1と名付けた。
2006年から、東京大学の國枝さんらと、このヨコヅナクマムシのゲノム解析のための研究をスタートさせることになる。まだ、この研究自体には何の研究費も付いていない頃だった。それでも、みんなでたまに集まって飲んでは議論したり、楽しい時期だった。
その後、私は博士号をとったものの、なかなかポジションが取れずにオーバードクターになった。クマムシにつけてもらえる予算はなかったのである。無給でゲノム解析のためのクマムシサンプルを育てたり、放射線耐性の研究をする日が続いていた。
結局そのあと、私はアメリカとフランスで計5年を過ごし、また日本に帰ってきた。慶應で非常勤として研究しながら、非専門家を集めたクマムシ研究所も主催したりと、割と不思議なポジションにいながらもクマムシの研究を継続している。
その間にも、慶應の荒川さんや東大の國枝さんのところのように、世界的なクマムシ研究の拠点と呼べる研究室もできた。そして、今回のヨコヅナクマムシのゲノム解読の、10年越しの研究論文発表。クマムシ研究にひとつの節目をつけられたようで、本当に感慨深い。クマムシの研究を始めた学部生の当時、このような日が訪れるとは予想できなかった。
また、Dsupについては機能解析を進めた橋本さんの仕事の成果で、これも当初はリスクの高いテーマだと思われていた。
私がクマムシ研究を始めた頃は、よく否定的なことを言われたものである。「クマムシは研究というよりは趣味の世界」と言われたこともある。それでも、たくさんの人に支えてもらい、今でもクマムシの研究をすることができている。私が作った実験系を使って、クマムシの研究をしている研究者や学生もいる。クマムシ研究所とBioClubのワークショップでは、小学生から社会人まで幅広い層の人たちが研究をしている。
当時の私は、大学院に進んだ学生の中でも、だいぶレールから外れた研究テーマを選んだ。一歩間違えれば、学位が取れずに研究者としてはとっくに死んでいただろう。だが、そういうバカな人間だって、人柱として必要なこともある。私が成し遂げてきたことなどたかが知れているが、それでも曲がりなりにも、自分の研究が誰かの研究に役に立っていたりする。
バカが勘違いをして始めた研究がそこそこの成果を生み、そこに色んな人たちが絡んで、またさらなる研究の広がりを見せる。今回の研究成果もまた、他の研究に役立ったり、将来は思いもよらないような用途に応用されることだってあるかもしれない。
だから、ありきたりなことに聞こえるかもしれないが、多様な研究ができる環境というのはとても大事なのである。その環境は、単純に予算だけで解決出来る問題ではない。レールから外れているように見える人たちを嘲笑する風潮をなくすことも、そんな環境作りには必要だろう。バカにやさしい環境作りである。
もし、この記事を見ている貴方が学生で、レールから外れたいと思っているなら、外れてみるのもいい。失敗しても後悔しないと、自分に約束できるなら。
【参考資料】